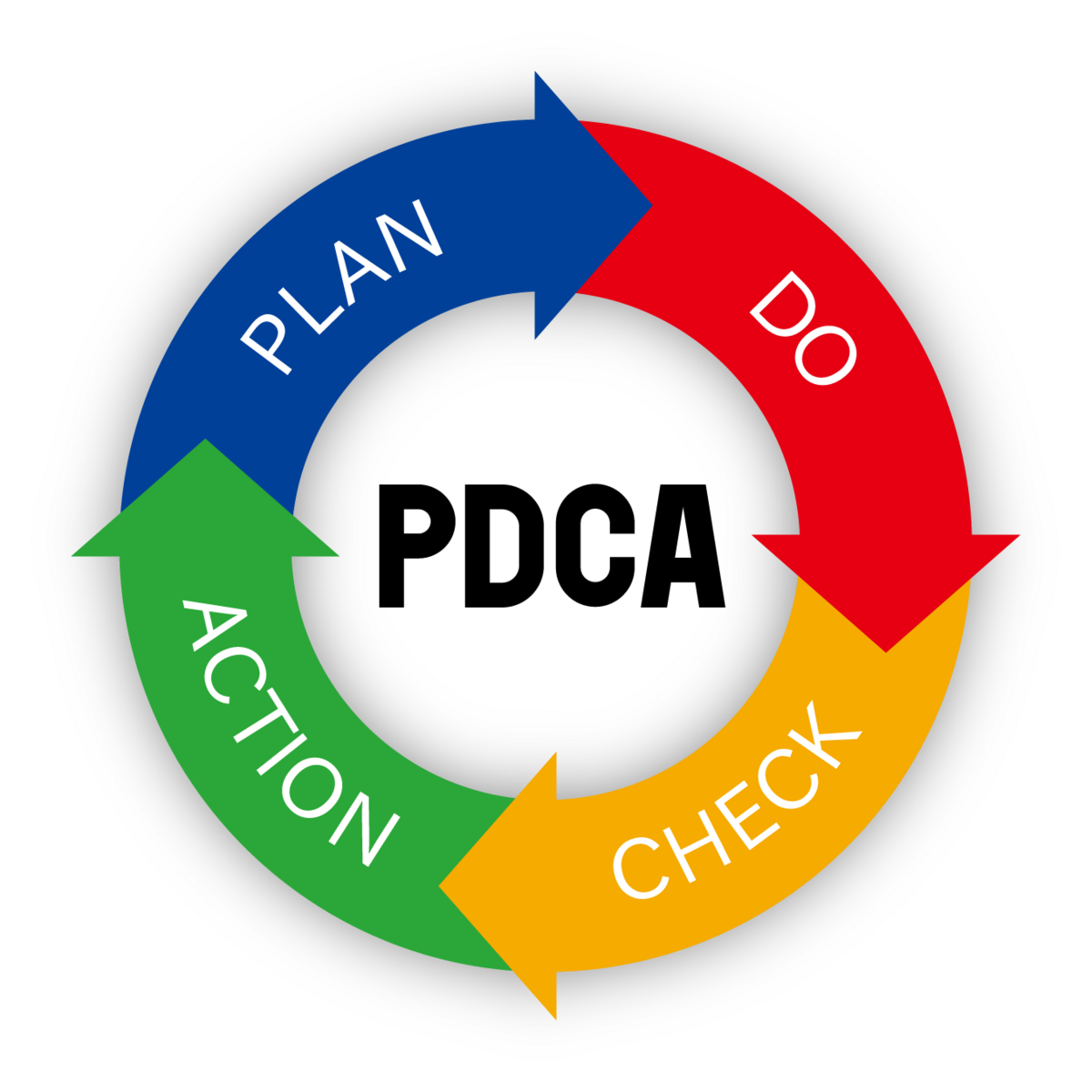今回は、「俺か、俺以外か。ローランドという生き方」(2019年)を読みました。
私はテレビを見ないので、どこのどなたか知らなかったのですが、ホスト界の帝王と呼ばれる人だそうです。

彼の名言が面白くて、勉強になったので、私の気に入ったものをまとめたいと思います。
本書のタイトルにもなっている言葉ですね。この言葉は、実は幼少期から使っていたそうです。自分は特別な人間だと感じ、どこにも属さないし属したくないと心から願う一方で、「俺以外」として生きるほうが何倍も楽だろうとも述べています。
唯一無二の「俺」でいるために、めちゃくちゃ努力されている方だということが分かりました。
彼は大学に進学したものの、入学式を最後に退学届けを出し、歌舞伎町でホストになりました。
彼の父親もまた、小学校の担任から給食を残すことを電話で指摘された際に、
「好き嫌いが多い?なんでも好きだとか、どっちでもいいって言う人間の好きという言葉に、いったいなんの価値がありますか?嫌いなものを、しっかりと嫌いと言えない男にはなるな。そう教えています」
と言い返したのだそうです。この親にしてこの子ありですね。
自分ではない誰かの意見に流されるのではなく、常識を疑い、自分の頭で考えるということが大事だということだと思いました。
これは分かりますよね!
彼はタキシードにはかなりのこだわりがあるそうで、イギリスの名店ハンツマンのビスポークのものを着ているそうです。「タキシードをカッコよく着られない男は、男じゃねえ」とも述べており、なりたい自分になれということだと思いました。彼は、「自信を持てとは言わない。自信のあるふりをしな!」とも言っています。

女性で言うなら、高いヒールといったところでしょうか…。私もヒールの似合う素敵な女性になりたいのですが、高いヒールを履くと小鹿のようになるので、、、これから練習しますw。毎日お化粧して、自信に満ち溢れたイイ女のフリをしましょう。

彼は女性から「貴方のことが好き」と言われるたびに「俺も好きだよ!」と答えていたそうです。
そう、「俺も(ローランドのことが)好きだよ」という意味で(笑)

これは、正月に親戚一同が集まった際に、酔った親戚の一人から「金髪にすることは、親にもらった髪の毛を粗末に扱う行為だ」「親の育て方が悪い」と両親をもバカにされた時に返した言葉です。
彼はトレードマークとも言えるブロンドのロングヘアに並々ならぬこだわりがあるようで、トリートメントも3日で1本使ってしまうのだとか…。
なお、この発言はめっちゃウケたそうです。このような臨機応変なユーモアは高校生時代(体育コースでサッカー漬けだった)に培ったということでした。
嫌味をユーモアで返すセンス、私も欲しいです。
本書を読んで、どんな仕事でも、理念を持ち、未来の姿をありありとイメージすることが大事だなと思いました。大学を辞める時も、ホストの下積みで辛い時も、ローランドは「自分はどう生きたいのか?」と自分に問い、自分中心で生きてきたということがよく分かりました。
「これまでの嫌な人との出会いや辛かった経験に心から感謝できる日が来る」というのは、まるで修行を積んだ僧侶のようです。このような人物だから、憧れる人も多いんだろうなと思いました。真似はできないけど、かっこいい生き方だなぁと思います。




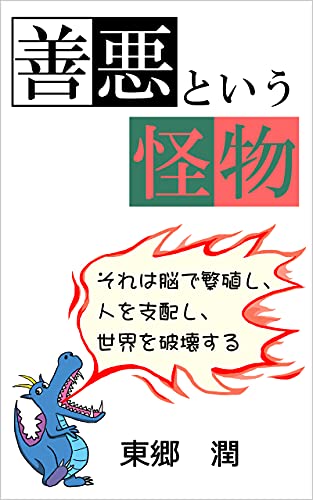


















![[新訳]留魂録 [新訳]留魂録](https://m.media-amazon.com/images/I/41ufVGqPikS._SL500_.jpg)